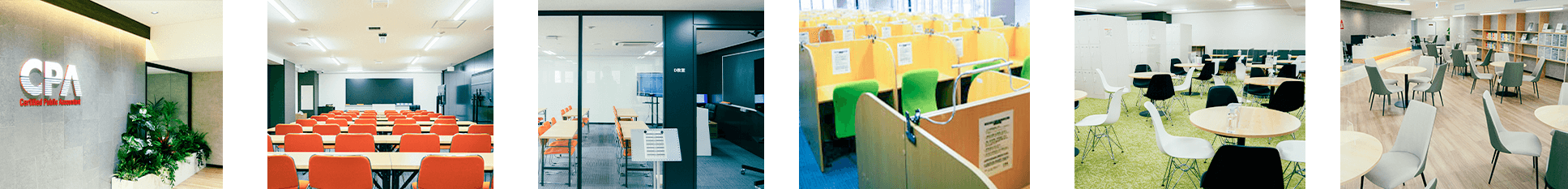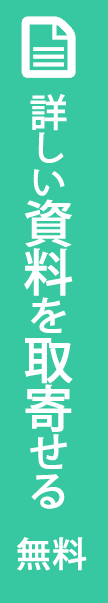財務会計論 渡辺克己 講師
財務会計論 渡辺克己 講師

プロフィール
平成7年慶應義塾大学経済学部卒業
公認会計士受験指導歴23年
財務会計論の計算(簿記)と理論(財務諸表論)をともに担当し、いずれも作問と講義を行う
平成5年公認会計士第2次試験合格、公認会計士
財務会計論は短答式試験・論文式試験ともに最も配点の高い科目です。
その重要な科目を預かる立場として、講義は言うまでもありませんが、教材の作成や答練・模試の作問に至るまで、すべてにおいて真剣勝負していきます。僕の講義や教材を選んで下さった受講生の皆さんの期待を裏切ることがないよう、頑張らせていただきます。
@kw_cpa渡辺克己講師 担当講座
本科コース
| 講義名 | 上級本科コース | 短答受験コース | 上級論文マスターコース |
| 短答対策講義 財務会計論(計算) |
〇 | 〇 | – |
| 短答対策講義 財務会計論(理論) |
〇 | 〇 | – |
| 論文対策講義 | 〇 | – | 〇 |
CPAの本科コースなら、各科目の学習習熟度に応じて、『圧縮講義』『レギュラー講義』、『短答・論文対策講義』を自由に受講可能 (無料)。
受講する講義の種類は、科目ごとに、範囲ごとに「完全に」自由に選べます。詳細はこちら
オプション講座
会計士受験界の新たな計算スタンダード教材とすべく、渡辺克己講師が開発した『計算コンプリートトレーニング』。
渡辺克己講師が自信を持ってお届けするこの教材を、受験勉強の良きパートナーとしてお役立てください。
短答対策講義 財務会計論(計算)
CPAの本科コースなら、各科目の学習習熟度に応じて、『圧縮講義』『レギュラー講義』、『短答・論文対策講義』を自由に受講可能 (無料)。
受講する講義の種類は、科目ごとに、範囲ごとに「完全に」自由に選べます。詳細はこちら
概要
短答式試験の対策に特化したインプット講座です。短答式試験の勉強に時間を割きたい方や、なかなか短答式試験の壁を乗り越えられない方にお勧めする、シンプルに合格点を確保することを目的とした講座です。
特徴1 「徹底した理解の重視」
計算に関して言えば、「分かる」と「解ける」はイコールではなく、「分かるのに解けない」ことや、「分からないのに解ける」ことが現実的にあり得ます。ここで、「分かるのに解けない」よりも「分からないのに(解法を覚えたから)解ける」方が得点に結びつきそうに感じられますが、このような短期的な視点による講義は目指していません。一つ一つの会計処理について、「なぜそうなるか」という理論的背景を、しつこいほどに説明します。「分かる」は、いずれ「解ける」へ繋がる道であり、「解ける」状態を長期間保持する役目も有します。そして、この「なぜそうなるか」という理解は、理論の学習、更には合格後の実務においても強力な武器となると考えます。
特徴2 「論点の性質に応じた最適な対策」
短答式試験の合格を最優先に考えた上で、論点を大きく「連結」「組織再編」「その他」に分類し、それぞれの性格に応じた最適な対策を行います。具体的には、各論点とも背景にある考え方を重視しつつ、「連結」はパターンごとの解法習得、「組織再編」は連結視点での基本的思考の確立、「その他」は徹底したリスク・アプローチによる合格点の追求です。すべての論点を同じように扱うのではなく、理解重視の方針の下で、戦略的に各論点を攻略します。
特徴3 「計算と理論の同一講師による講義」
公認会計士試験には簿記や財務諸表論という科目はありません。あるのは財務会計論という科目だけなのです。受験予備校では便宜的に財務会計論を計算と理論を分け、それぞれ専門の講師が講義を行いますが、同じ科目である以上は同一講師による一貫した説明に基づく講義が行われることが理想です。短答対策講座では、財務会計論の計算と理論を同一講師が担当することにより、「計算の学習時には理論的背景を意識し、理論の学習時には計算の処理を想像する」という、理想的な学習が可能となります。
対象
短答式試験を受験予定で、短答特化型の対策を行う財務会計論(計算)の学習経験者
講師からのコメント
公認会計士試験の対策については、短答特化型の対策と短答論文並行型の対策の2つの方法が存在します。どちらが適するかは各自の受験環境及び受験戦略に左右されるため、絶対的な正解は存在しません。短答対策講座は、あくまで短答特化型の受験生を対象とした講座です。合格者が口を揃える「勉強は論文のときの方が大変だったが、振り返ってみると短答の方が高い山だった」という言葉は、運の要素が多分に含まれる短答式試験の方が、論文式試験よりも試験として怖いことを表していると思います。この短答式試験に全力で立ち向かう受験生に、本試験で合格点を確保するための道筋を示していきたいと考えています。
※テキストのほか、オリジナルレジュメを用いて講義を行います。
サンプル動画
短答対策講義 財務会計論(理論)
CPAの本科コースなら、各科目の学習習熟度に応じて、『圧縮講義』『レギュラー講義』、『短答・論文対策講義』を自由に受講可能 (無料)。
受講する講義の種類は、科目ごとに、範囲ごとに「完全に」自由に選べます。詳細はこちら
概要
短答式試験の対策に特化したインプット講座です。短答式試験の勉強に時間を割きたい方や、なかなか短答式試験の壁を乗り越えられない方にお勧めする、シンプルに合格点を確保することを目的とした講座です。
特徴1 「基礎概念の重視」
財務会計論は少数の基礎的な概念を押さえることによって、理解の範囲を広げ質を高めることができます。この少数の基礎的な概念から各論点を理解することにより、暗記すべき量を軽減させることが可能となります。短答式試験を暗記主体の単なるマルバツ試験とは考えず、基礎概念から理解するものと位置付けることで、論文式試験にも繋がる知識を得ることができます。
特徴2 「過去問の重視」
理論では、過去に出題された肢が再度出題されることが珍しくありません。中には5回以上も出題されている肢もあります。過去問を重視し、過去問から逆算して重点的に対策すべき範囲とそうでない範囲を明確にすることで、膨大な学習範囲に重要性の色分けを行うことができます。また、講義では随時過去問に触れるため、今学習している内容がどのような形で出題されるかを具体的に感じ取ることができます。
特徴3 「計算と理論のリンクの意識」
計算と理論を同一講師が担当するため、理論の講義の際には「計算でもこの説明を聞いた」と感じることが多々あるはずです。「計算の学習時には理論的背景を意識し、理論の学習時には計算の処理を想像する」という理想を追求するために、計算の内容を想起させるような説明を行います。そのため、計算と理論が有機的に結びついた知識を身に付けることができます。
対象
短答式試験を受験予定で、短答特化型の対策を行う財務会計論(理論)の学習経験者
講師からのコメント
短答式試験における計算と理論の過去の出題を比較すると、理論の方が得点しやすい回が多く、計算よりも理論の方が得点を安定させやすいことが分かります。このため、財務会計論で合格点を確保するには、理論の安定が必要不可欠といえますが、財務会計論の理論については、短答式試験と論文式試験では全く異なる力が要求されるのです。したがって、短答式試験での得点の安定のためには、短答式試験向けの勉強を行う必要があります。計算ほど多くの勉強時間を割けない理論では、効率性が計算以上に求められますので、基礎概念と過去問を重視し、計算とのリンクを意識することで、効率的に合格点を確保できるような道筋を示していきたいと考えています。
※テキストのほか、オリジナルレジュメを用いて講義を行います。
サンプル動画
論文対策講義 財務会計論(理論)
CPAの本科コースなら、各科目の学習習熟度に応じて、『圧縮講義』『レギュラー講義』、『短答・論文対策講義』を自由に受講可能 (無料)。
受講する講義の種類は、科目ごとに、範囲ごとに「完全に」自由に選べます。詳細はこちら
概要
論文式試験の対策に特化したインプット講座です。膨大な範囲を有する財務会計論の理論を、「理解」と「過去問」を鍵にコンパクトに整理し、シンプルに合格点を確保することを目的とした講座です。
特徴1 「基礎概念の重視」
財務会計論は少数の基礎的な概念を押さえることによって、理解の範囲を広げ質を高めることができます。この少数の基礎的な概念から各論点を理解することにより、記憶の定着率が向上するとともに、思考型の問題にも対応できる力を身に付けることができます。
特徴2 「過去問分析のフィードバック」
過去問を分析すると、出題論点に露骨なまでの偏りがあることが分かります。これは講義において論点ごとに強弱をつける際の参考にしています。また、出題される問題は、①簡単な知識吐き出し型、②難しい知識吐き出し型、③簡単な思考型、④難しい思考型に大別できます。このうち、シンプルに合格点を確保するために必要な①と③の攻略方法を、過去問から読み取って講義に反映させています。したがって、論文対策講座を受講することにより、徹底した過去問分析の結果を自動的に学習にフィードバックすることができます。
特徴3 「計算を含めた傾向に基づく対策」
論文式試験の財務会計論は形式が安定せず、計算と理論のウェイトが一定ではありません。そのような中で計算と理論を一体として分析せず、それぞれを専門の講師が講義するような講座では、計算と理論の双方で受講者に過大な負担を課しがちです。計算と理論の双方を担当する講師だからこそ、財務会計論全体を見渡す視点に立ち、その傾向に即した講義を提供します。
対象
論文式試験を受験予定の方(初回受験者も含む)
講師からのコメント
論文式試験の勉強で最も重要なことは、ハードルの高さを適切に設定することだと考えます。得点の比重が最も重い財務会計論は、その範囲が膨大ですので、学習し始めの受験生にはとても手強く感じられるでしょう。しかし、本試験では素点で5割程度取ることができれば十分にお釣りが来ます。できなくてもいい問題があることを正しく認識し、「できるべき問題をできるようにする」ことに注力することが、合格点への近道です。そのための道筋を示していきたいと考えています。
※テキストのほか、オリジナルレジュメを用いて講義を行います。