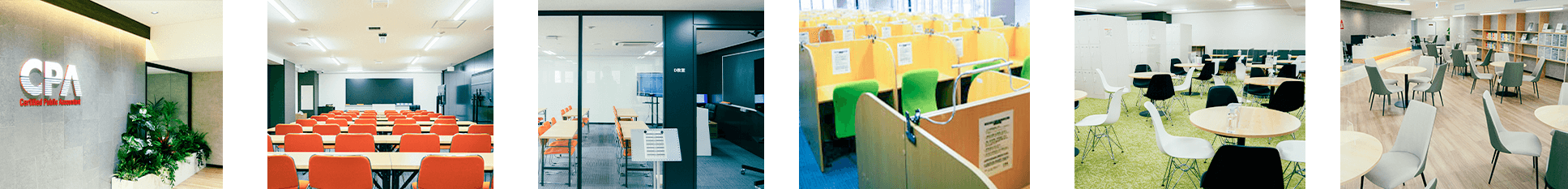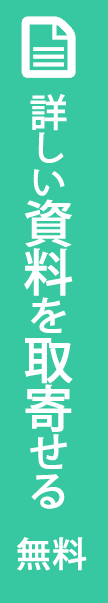財務会計論(計算)講師 国見 健介

我々講師陣の役割は、皆さん一人ひとりが合格できるように、強力にサポートすることです。そのためには、講義、教材、試験に関する情報について、高いクオリティーのものを提供することが求められます。
講義・教材・個別フォローで徹底的に高い品質を追求していきますので、一緒に公認会計士試験の合格を勝ち取りましょう。
「分かっているが解けない・・・」から「実際に解ける」実力をつける講義
「考え方」から押さえ、点数に直結する「解法」まで解説
近年の財務会計論の計算は出題範囲が拡大しているため、皆さんの負担は非常に大きくなっています。また、計算科目特有の「論点は分かっているが本試験では解けない」(解答を見れば分かるが…)という状態のため、財務会計論(計算)で高得点を取れない方も多いと思います。
そのため私は、講義を通じて、皆さんの財務会計論(計算)の実力を、「分かる」から「実際に問題が解ける」レベルまで引き上げることを目的にします。
「考え方」から押さえ、点数に直結する「解法」まで解説
まず講義では、各論点ごとに、背景となる考え方(財務諸表の構造・意味や実際の取引形態)からしっかりと説明を行い、さらに豊富な具体例を用いることで、効率的に具体的な会計処理や計算方法が理解できるようにしています。
そして、講義内では設例を解く時間を多く取り、その解説を通じて、アウトプットする際の留意点や点数に直結する解法まで解説していきます。また講義後に、個別計算問題集・短答対策問題集を解くことにより、実践的な問題への対応力を飛躍的に向上させることが可能となります。

高い得点力を養う学習法は理解を伴ったアウトプット対策が理想
このように、正しい理解を伴った上で、アウトプット対策を豊富に積むことこそが、本試験で確実に合格点以上の高い得点を取るために、最も効率的な方法です。
また、その結果、皆さんは、広範な出題範囲となっている財務会計論(計算)に費やす時間を大幅に削減でき、効率的に学習を進めることが可能となります。
財務会計論(計算)を得意科目にすることは、本試験で大きなアドバンテージを得るのみならず、実務に従事する際にも非常に重要なことです。そのため、是非財務会計論(計算)が得意になった状態で合格していただきたいと思っています。
私の講義を受講した方が、「財務会計論(計算)が得意になった」と確信できる講義を提供していくことで、皆さんの合格を強くサポートしていきたいと思っています。
よくある質問
苦手な科目の場合どのように学習すればよいか?
財務会計論(計算)が苦手な場合は、量をこなしてカバーしようとしがちですが、範囲が膨大であるため、しっかりと理解をすることがお勧めです。そもそも何をやっていて、財務諸表の結論はどうなっているのか、簿記の5 要素の関係性と合わせて押さえていきましょう!かつ疑問点はなんでも質問して解決することがお勧めです。
科目においての理解重視の学習とは?
財務会計論(計算)は、企業の取引の記録の仕方、成績表の作成方法を学ぶ科目です。そのため、財務会計論(計算)が苦手な場合には、取引のイメージを具体的に明確にすること、財務諸表の結論をしっかりと確認することがお勧めです。特に複式簿記の構造である2 面的にとらえる視点を大切にすることで理解が深まります。
科目において重要性をどのように意識して学習すればいいか?
財務会計論(計算)は、ボリュームが最も多い科目ですが、他の科目以上に、重要論点が頻出されやすい科目です。論点ごとにどの程度本試験で出題されているかは、テキストに細かく明示しているので、重要論点をまずはしっかりマスターしていってほしいと思います。重要論点は、どう出題されても得点できるレベルを目指していきましょう!
短答式試験突破のための勉強法?
短答式試験で重要性の高い論点を徹底的にマスターしてきましょう!それに加えて、短答式試験は時間との勝負なので回答が求められている数値をダイレクトに算定できる練習を積むことがお勧めです。テキストの例題で、知識の定着と、解法の定着を徹底的に強化することで、スピードと正確性が高まります。その確認を短答対策問題集と答案練習で実践してほしいと思います。
論文式試験突破のための勉強法?
論文式本試験突破のためには、重要性の高い個別論点の定着と総合問題対策が必要になります。
総合問題は、連結会計を中心に、組織再編、キャッシュ・フロー計算書を構造の理解から得意論点にしていくことが求められます。最近の試験傾向では、集計能力よりも、問題の出題意図と出題構造を把握し、問題の解き方を早期に見極める能力が大切なので、普段の学習でその力を養ってほしいと思います。